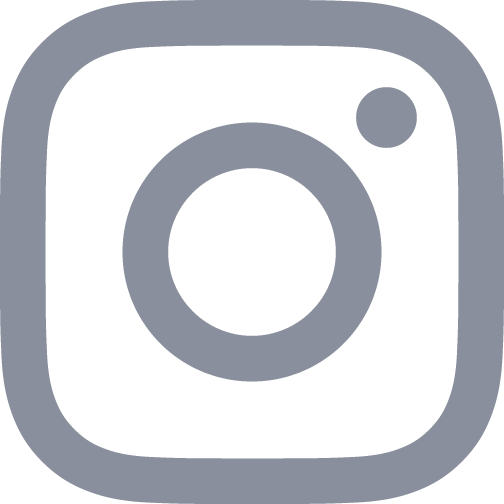テキスト
藤野裕美子は過疎の地域の廃屋などを取材して、家財道具や日用品、放置された庭の植物など、そこに遺されたさまざまなものを画面上に配置するという方法で作品を制作してきました。そうした種々のものは、そこにかつて暮らしていた--そして今はもういない--人たちが遺していった生の痕跡です。画面上で再構成されたものたちは、それらがかつてあった本来の場所や、それらの固有の大きさから自由になり見かけの遠近法ではなく、いわば記憶の遠近法によって新たな関係を紡ぎ出します。裏表紙には、滋賀県立美術館での巨大なインスタレーションから、植物と赤い着物が織りなす超現実的な出逢いを描いた細部を選んでみました。
文・同志社大学教授 視覚文化研究者 佐藤 守弘
2024年
日本各地の地域芸術祭やアーティスト・イン・レジデンスなどで、地域に滞在し、生活圏に残る文化風習や記憶のリサーチを基に制作する作家は少なくない。藤野裕美子は、そうしたリサーチ型アートと日本画の交差点として位置付けられる。
藤野は瀬戸内海の島、滋賀県の湖西地域、奈良県の明日香村など、過疎の地域や廃屋を取材し、残された家財道具や生い茂る植物を、日本画材を用いて点描風のタッチで丹念に描く。その際、異なる地域や時代のモノどうしをコラージュのように組み合わせる点が特徴だ。
廃屋のなかには、戦前から時間が止まったままの家もあるという。一方、旺盛に繁茂する植物は、人の営みが絶えた後も時間の流れが続くことを示す。色鮮やかな画面の中に、過去と現在、時間の停滞と更新が交錯する。コラージュとは文脈からの切断と再接続の操作だが、藤野の作品は、「時間」のコラージュでもある。そこでは歴史の重みという「重力」から事物が解放され、自由に漂うような浮遊感に満ち、あらゆるものが等価で重さのないデータとして漂うバーチャル空間を思わせる。
一方、画面の中には戦前の軍国主義のスローガン「八紘一宇」の文字も一部見える。スローガンが表記された急須と湯呑みのセットは、丁寧に包まれた状態だったという。なぜ、持ち主は大切に所有していたのか。「戦争」が日常生活に溶け込んでいたこと。そうした想像力が渦巻き、めまいを感じさせるような絵画の無重力空間を生み出している。
文・美術批評家 高嶋 慈
2023年
PDF:置かれる身 行き交う眼 -from unwelt-
文・美術家 葛本 康彰
2022年
「ハサミで切って糊で貼る」、という行為は誰しもが経験したことがあるだろう。その経験の多くはイラストを切って別の媒体と貼り合わせたり、箱などの立体物を組み立てたりした子どもの頃の工作体験が大部分を占めているように思われる。そのような共通する工作体験を念頭に、今年度の本展のテーマは「点線とのりしろ」とした。点線はミシン目や鎖線とも呼ばれ、点が一定の間隔に並んだもの。そしてのりしろは繋ぎ合わせるために糊をつける部分であるが、遊びやゆとりといった意味も持ち合わせ、両者とも工作などの際に必要となる目印である。「コラージュ(切り貼りする技法)」「つぎはぎ」「寄せ集め」といった単語とほぼ同義のテーマでありつつも、創作行為の純粋な楽しさを損なわせない意図を込めた。今回出品する作家たちは日常の中にその点線を見い出し、それぞれの感性に従ってそれらを糊付けをしていく。3組ともその眼差しを向ける対象は異なっているものの、いずれも作家および私たちの日常生活に密接する物事を扱っており、当たり前でささやかな生活の延長線上に立ち現された作品たちである。
展示室1の中央に櫓のようにそびえ立つ藤野の「まじらう地点」は、約4mの高さを持った日本画のインスタレーションである。 藤野はステートメントに記載している通り、各地での取材を通して発見した物事を描いている。今回の作品で描かれているモチーフは、たとえば中身が不在の薄紅色の晴れ着、戦時中に掲げられていたであろう一億一心の看板、カラス避けらしき反射材のようななにか、庭先で成長したアロエ、など。その土地で古くから残され続けてきたものや片隅にひっそりと忘れ置かれたものが選び出されているため、ひとつひとつのモチーフからは前時代的かつ退廃的な感触が伺える。藤野はそれらを画面上で構成し、さらに人知れない場所で繁殖する植物の息吹や、接続や関係を象徴する紐を描き込むことで、鮮やかな色使いと共に寂びれと孤独をあらたに繋ぎ止めた世界を描き出している。また、藤野は作品の裏面をあえて観せる形を取っており、その構造は日本の伝統的な住まいを想起させる。襖や衝立のように裏表など様々な角度からの干渉が可能となることで、彼女の言うように鑑賞者の視点や想像上で画面内外のイメージはさらに幾重にも交錯していき、隙間からはよしだとたかだ、田代の作品を覗き観ることもできる。
軽快なアプローチで作品を制作するよしだとたかだは、展示室1では「レジャーシートのコラージュ」を正面のガラス一面に展開した。作品自体の作りはシンプルで、既製のレジャーシートを丸や四角や三角に切り、違う柄の物同士を縫い合わせて作られた作品である。今回はその2~4人用サイズを壁面全体に繰り広げた。展示室2の作品もタイトル通り、夫婦と長女長男の4 人で暮らす作家の自宅にあったあり合わせのもので作られたモビールである。「そこにあるものに少しだけ手を加えて、ちょっと面白いものにする」という彼らのコンセプトはそれ以上でもそれ以下でもなく、表層的な色や形の面白さを追求する姿勢を一貫 している。レディ・メイド(既製品をそのまま用いた作品)と呼ぶには手仕事の痕跡が強く滲み、キネティック・アート(動く彫刻) やオブジェと呼ぶには生活感が色濃く投影されており、かといって工業的に需要に対する供給の役割を担うわけでもない。よしだとたかだの作品は、アートとデザインと生活の間を軽やかに緩やかに揺れ動き、「なにかを作りたい」という人間の根源的な欲求を日々の生活の中に落とし込み地続きに成立させている。それ故に鑑賞者自身の視覚や感性にも触れる馴染みやすさがあり、 意識や記憶の中で想像を膨らませる楽しさを与えてくれる。
壁面に並べられた田代の「誰かのポートレイト(高島市)」は、レシートをこより状にし、綿糸で織ったものである。さらに注 意深く見てみれば、レシートの文字情報のディテールを確認することもできるであろう。田代の現すポートレイト(肖像画)は、その人物の消費生活の痕跡を織り合わせることで、明確な輪郭を持たせないままに人物の姿を浮かび上がらせる。モノ、サービス、お金が流れる消費社会の中で、田代はそこに生活する個人として、ミクロな経済活動からマクロの一端を捉えようとしている。経済・経営学が例えに使う森と木の関係を拝借すると、彼女は1枚の葉の視点から1本の木、ひいては巨大な森全体を感じ取ろうとしているのである。床に設置された「都市のポートレイト」は、自分や誰かがハンバーガー店でポテト を食べたり、ドラッグストアでビールを買ったりしたことが織り重なって形作られた姿であり、歪みやうねりを作りながらも流れ、 時間の経過に従い古いものは白っぽく情報が薄れていく。何年も昔にコンビニで買った些細な商品を覚えていないように、印字とともに記憶や商品自体も消失していくのだ。しかしその時に支払った小さなお金は今もどこかで流れ続け、社会のささやかな礎となっているのかもしれない。
彼らが切り取った日常の欠片のひとつひとつの共通項を探っていくと、日常の中でも必需品ではない(なくなった)もの、と読み解くことができるかもしれない。そして、それにも関わらず彼らはそれらが持つそのものの価値を変えずに、まったく別のイメージへと作り変えてしまうこともしない。自由自在に手を加えられる創作行為であったとしても、古い着物はあくまでも古い着物であり、レジャーシートも然りである。それぞれは必需品ではないものの、大なり小なりのなにかしらのエピソー ドを持っており、着物や看板には持ち主や土地の人々の歴史が刻まれ、レジャーシートやモビールには家族の計画や思い出があり、1枚のレシートにはその日その時の購入者と販売員の売買の記録が記されている。彼らは作品ごとに切り取った対象のそのような魅力を作品の大切な軸として、センスを元にした取捨選択や丁寧で繊細な手作業を通し、糊付けをしていくことで私たちを含めた新たな関係性を創造していくことに目的を置いているのである。藤野のように放置されたものから地域やその土地に住んでいた人たちを、よしだとたかだのように家にある日用品から夫婦や家族を、田代のように1枚のレシートから個人と社会に新たな関係性を見い出し作り出していくように、私たちもまた、目の前に点在する数多の物事を思い思いに糊付けしていくことで、面白さや楽しさが加わったより良い世界に出会い直せるのではないだろうか。
文・ 藤樹の里文化芸術会館 学芸員 花田 恵理
2022年
藤野裕美子の描くイメージは、廃屋や打ち捨てられた庭など、人の手を離れた後に自然に朽ちていくものをモチーフとしている。個々の事物は具象的であるが、それぞれのレイヤーが複雑に絡み合い、画面全体は一定の場所ではないどこかへ浮遊している。また。藤野の作品は日本画の技法によって絵画として描かれながらも、独特の展示方法によって壁に依存せずに空間に立ち上がる。その作品と相対すると、いつか昔にそこにいた描かれていない誰かの気配が、見るものを包み込む。
藤野は、展覧会のテーマを少し離れた位置から見つめるような制作コンセプトと、密やかな関係性を想起させる作品イメージから選出している。また現在、会場にほど近い共同アトリエ「Soil」に所属しながら制作をおこなっている。
今回出品された《みざかる地点》は、三つの菱形のイメージが会場内でレイヤーを作るように構成されている。特に作品の形状において特徴的な点は、統一したイメージの描かれた菱形も左右で二等辺三角形に分かれており、その間に10cm程度の隙間があけられていることだろうか。その間から次の菱形や小宮(同展覧会出品作家)の作品などが見え、ただ平面が空間に立ち上がるだけでは得られない複層的な作品の構造を作り出している。当初藤野は横並びの構成で構想していたが、奥行きのある細長い会場とその中に林立する複数の柱がある空間の特性から、レイヤーで作品と会場を構成するというキュレーターの案を見事に実現してくれた。
会場の周辺をはじめとした東近江の様々なエリアで採集されたモチーフで構成されたイメージは意図的に前後関係を混乱させており、独特の浮遊感がある画面を作り出している。また、それぞれの菱形は共通したモチーフで構成されてはいるが、隙間を埋めてもイメージが繋がらないように描かれている。
藤野の初めての試みとして、今回の作品は裏にもイメージが描かれている。能登川の織物工場で使われていた染め型を裏にあてて、胡粉で象ったものである。表のイメージとは全く異なった図像が浮かび上がっている。能登川の麻織物は夏用の布団や座布団を主に制作していたため、染め型の柄も涼しげな草木の柄であり、実際に使われていた頃が偲ばれる他、当時の染料が残っており胡粉が色ついている箇所もある。
展示の際には、三つの菱形の裏でそれぞれ、照明なし、スポットライト、自然光と光の質を変え、影となって浮かび上がるもの、キラキラと反射するもの、時間と天気によって刻々と見え方の変わるものなど、バリエーションを持たせた。
文・滋賀県立美術館 学芸員 荒井 保洋
2021年
新型コロナウイルス感染症に伴う最初の緊急事態宣言が出てからまもなく1年となる。1年前、ほぼ無人となった街にはピリピリとした緊張感が張り詰め、「非日常」が世界を覆っていた。現在は2度目の緊急事態宣言が出ているが、もはやそれが「日常」となってしまって、街にはどこか緩い空気が漂っている。「日日の観察者」はまさに「日常」をキーワードとした展覧会であり、参加しているのは、日々の生活の観察から得たものを作品化する4人の作家だ。タイトルはつまり作家たち自身のことであり、同時に作品を見る観客自身のことである。
花岡伸宏は制作を生活の延長線上に位置付け、日用品なども素材にしながら彫刻作品を制作しており、使われた素材をそのままタイトルにしている。会場であるHOTEL ANTEROOM KYOTO|Gallery9.5の中央には名和晃平の常設作品があるが、本作とコラボするように展示された《衣服、手、木材》では、生活の一部である衣服と名和の作品の表皮のイメージが関連付けられていた。藤野裕美子は道端や廃屋で見つけたモチーフと植物を組み合わせ、どこでもないどこかのイメージを描き出す。特徴的なのは仮設の骨組みによって絵画を空間に立ち上げる展示方法であり、《ちぐはぐな接点》では立ち上げられた絵画のあいだに立ち入ることさえできた。花岡と藤野の作品は、入場すると最初に目に入る。混然として空間を構成しており、壁によりかかる彫刻や、空間に立ち上がる絵画など、形態の転倒が興味深い。その空間の床に松元悠の作品の一部である石板とタペストリーが転がっている。松元は、マスメディアの取り上げるニュースの場所を実際に訪れ、観察者の立場からリトグラフを中心に作品を構成する。《在る碑(黒鳥山公園)》は黒鳥山公園をめぐる3つの作品から構成されている。戦争の記憶を語る3つの碑にまつわる「遺る碑」、交通事故死した娘が生前コンクリートに残した足跡をくり抜いた母親と、彼女が戦った裁判の記録にまつわる「お母さんの碑」、そして園内で発見された身元不明の頭蓋骨にまつわる「無名の碑」。入り口にあった石板とタペストリーは「お母さんの碑」に関わるものである。会場奥の壁面では、地図や書籍、メモや写真、イラストなどいくつもの断片が展開され、時代も来歴もまったく異なる3つの要素が、黒鳥山公園という場所と松元を通して組み上がり、展覧会のなかでも異色の迫力を放っていた。小出麻代は、時間や記憶にかかわる作品を発表している。《別の言葉で(氷とコップ)》、《別の言葉で(カーテンと窓)》、《別の言葉で(拾い物と影)》と題された3点の作品は、どれも小出による日常の記録の結果であり、まるで激変する日常に流されまいと自身をつなぎ止めるようとするものであるかのようだ。取り戻すでもなく新しいでもない、別の言葉を探しているとステイトメントで本人が語っているように、小出は自身の日常と現状の日常の間に齟齬を見出して、それを言葉にならないまま、素直に表現にしようとしている。
また、本展はInstagramアカウントを開設し、会期前の2020年8月1日から会期が終了する1月10日まで、同日の同時間に作家それぞれが定点観察として写真を投稿していた。昼食後の箸先をアップする花岡、出品作をつくる小出、別の展示のハンドアウトを校正する藤野、職場で休憩する松元。作家の目を通した日常が複眼的に展開されていくInstagramから感じられたのは、コロナウイルスが出現する前の日常が変わらず継続されているという、ある種の錯視的な安心感だった。そして会場で配布されたハンドアウトには、キュレーターの伊藤まゆみによる各作家へのインタビューと、作家同士によるリレーインタビューが掲載されている。もしかしたらイベント開催を断念したことの代替だったのかもしれないが、これらのテキストは、それぞれの作家のバックボーンやいち個人としての存在感をより意識させるものになっていた。Instagramやハンドアウトが、作品と作家の生、そして作品同士の関係性を明確にし、展覧会全体の構造を強化していた。本展から見えてくるのは、日常化する非日常の姿ではなく、むしろその背後で淡々と歩を進めるかつてと同じ日常の姿である。社会のラディカルな変化に自身の体を少しずつ馴染ませていく小出や、日常を淡々と歩む強さをもった花岡や藤野、日常に潜む記憶を観察者の目線からフラットに拾い上げていく松元。彼らは社会の構造が揺らぐなかで、目先の変化にいたずらに踊らされ、その外形をなぞるのではなく、これまでの歩みの延長にある淡々とした日常のそれぞれの場所から、じっと変わりゆく日常を見つめている。社会全体が大きな変化にさらされるいま、そうした変化を敏感に感じ取りリアクションする表現に対して、本展において示された日常に対する視線や表現は、いつか現状の変化が落ち着いたあと、あるいはいまの非日常がさらに日常化してしまったあとも、その輝きを失うことはない。
文・滋賀県立美術館 学芸員 荒井 保洋
2021年
藤野が2019年の瀬戸内国際芸術祭で発表した絵画作品は、古い家屋にその記憶と命を蘇らせるために描いたものだった。藤野は、絵の中に他者の物語を映し出す。鑑賞者は、過ぎ去った時間の記憶、そこに確かに存在したものの余韻や感触を未知の他者と共有することができる。廃屋や空き家、作品が置かれる場所がどこであっても、彼女の作品は過去と現在を繋ぎ、さらに未来までも感じさせてくれるのだ。これからの活動が楽しみな作家である。
文・美術家 塩田 千春
2021年
(一部抜粋)
藤野裕美子の作品もまたユーモアを伴ってこちらへ飛び込んでくる。《ちぐはぐな接点》は木材を使った2組の構築物に日本画を「展示」した作品である。観客を誘惑し、絵と絵の間を通り抜けられるようにしたかと思えば、もう一方では観客の視線だけが通り抜けるしかないサイズだったり、この2組の木造構築物という工夫によって、絵を見るとはなんだろうね、と、こちらに問いかけてくる。絵に簡単に集中できない。木造構築物の存在が気になって仕方がないからだ。しかしそのことによって、我々観客は、絵を見逃すまい、と思う。絵画というものが重さがあり、イメージだけが浮かんでいるのは決してない、物質であることを意識するだろう。重力を無視して地面ごと浮遊しているような、絵に描かれている光景が、奇妙な切実さを伴って見えてくるはずだ。壁を自明のものとしない木造構築物の存在は、絵を見る三次元空間という人間の安全地帯を、緊張感のある場所へと、変貌させる力を持っていた。(ちなみにもう一点の出品作《九条の交差》は一見壁に展示されているようであるが、よく見ればそこは「柱」である。作者の機知がこんなところにも感じられる。)
文・小説家 福永 進
2021年